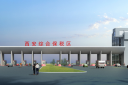時は戦国の末。天下を狙う列国の諸侯達は、競って一芸一能に秀でた者たちを客分として招き集めた。これがすなわち食客である。わけても斉の孟嘗君は数千、楚の春申君は三千余、趙の平原君は数千、魏の信陵君は三千と、食客の数を誇ったものであった。
しかもこの食客達は、今日の居候とは違い、いずれも一癖も二癖もある人々であり、諸侯達にしても彼らを自分の許につなぎ止めておくために様々の苦心をした。たとえば、家産をなげうって諸侯の食客を膝下に集め、「天下の士を傾けた」とまで言われる孟嘗君は、貴賤の別なく、全て自分と同等の待遇をし、また彼らと話すときには常に祐筆を屏風のかげに控えさせて、彼らの話中からその親戚の住所を書きとめさせ、後で人をやって進物を届けさせたという。
またこんな話もある。趙の平原君が食客を外交使節として、楚の春申君の許へ派遣した時のことである。平原君の食客は自分がいかに趙で優遇されているかを誇ろうとして、わざわざ玳瑁の簪を作らせ、佩刀の鞘には珠玉をちりばめたものを用い、美しいいでたちで春申君の食客に対面を申し入れた。ところが、出て来た相手を一目見た途端、彼はあっと赤面した。というのは、春申君の主だった食客達が、揃いもそろって珠玉をちりばめた靴を履いていたのである。
さてこの頃、諸侯に負けてはと躍起になって食客を集めた男がある。
一介の商人から身を起こし、今は強国秦の相国(総理大臣)となり、弱年の王政、すなわち後の始皇帝を操って威勢を振るっていた呂不韋である(呂は実は始皇帝の父親である)。

始皇帝の父、荘襄王が妾腹の子であったため、趙の国へ人質にやられて小遣いにも事欠くような生活をしていたときに、「奇貨居べし」と目をつけて莫大な投資をし、ついに今日の栄華を勝ち得た呂不韋のことだ、信陵君、春申君、平原君、孟嘗君が盛んに食客を集めてその数を誇っているのを耳にしては黙っていられない。
「強大をもって鳴る我が秦国が、こんな事であいつらに見下げられてなるものか」と、そこは商人、金に糸目をつけずに食客を招いたので、各地から集まって来た者は三千に達した。
こうなると、ますます彼の欲はふくらんだ。この頃、各国で賢者たちが著書をあらわし、特に斉?楚に使えた儒者の荀卿なぞは、蜀世を嘆いて数万言の書物をあらわしたと聞くと、「よし、ひとつ俺もやってやるか」という気になった。そこで食客たちに命じて作らせたのが、二十余万言よりなる大冊である。
「どうじゃ、天地万物古今のことは、全てこの中に入っておる。こういう大仕事が、わしでなくて誰に出来る」と鼻を高くした彼は、この大作を自分の編集したものとして『呂氏春秋」と題した。その上に、やったことが面白い。この『呂氏春秋」を都咸陽の城門の前に陳列させ、その上に千両をぶら下げておいて、大きな張り札を出した。
「能く一字を増損する者あらば、千金を予えん。」
つまり、この本の文章を添削できた者には、一字について千金の賞金を出すというのである。いかにも人を馬鹿にしたやり方だが、これも実は商魂たくましい彼の食客誘致策だったのである。(?史記?呂不韋伝)